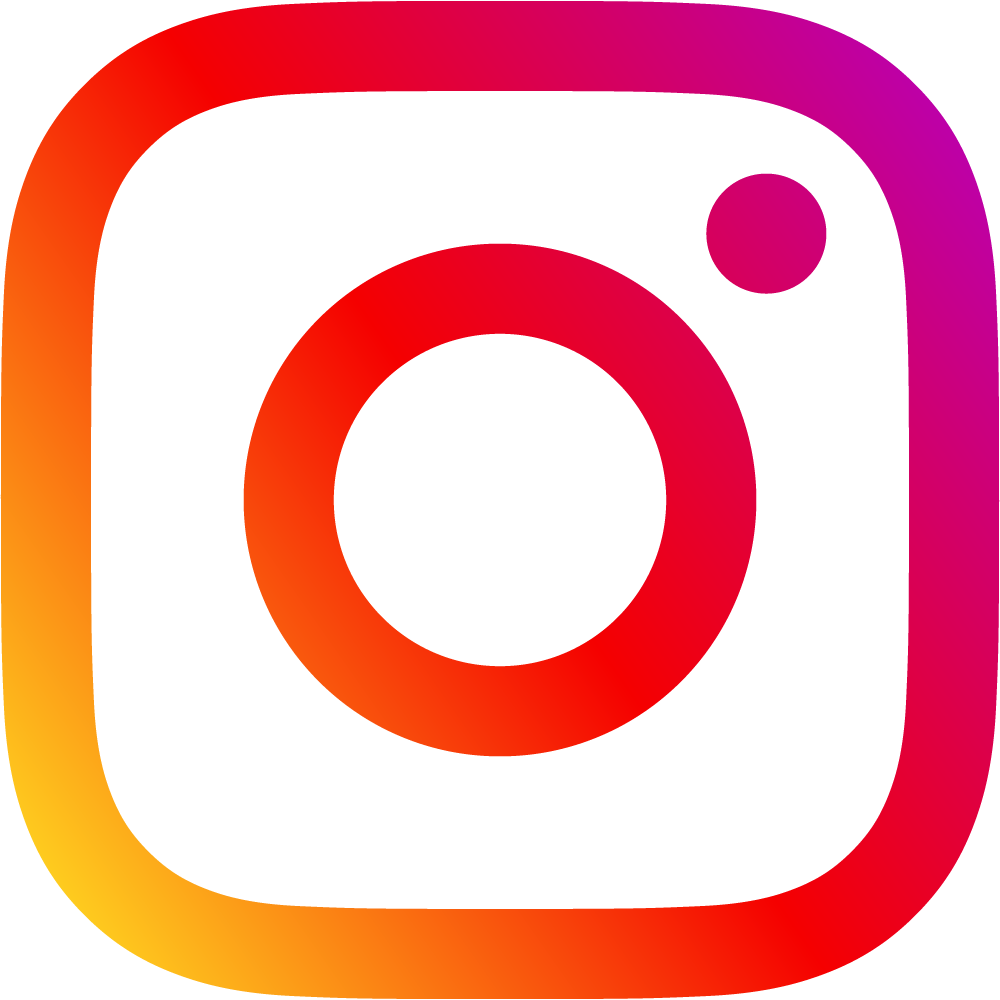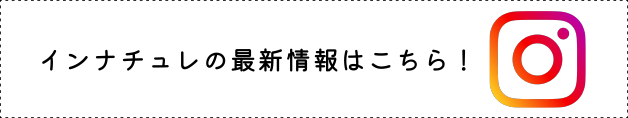第9回もっと、おいしい家庭菜園! 畑の土づくり

第9回 もっと、おいしい家庭菜園! 畑の土づくり
みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
みなさんにとって
野菜づくりの1番の楽しみって、なんですか?
大きくなる野菜の姿を見るのは
もちろん楽しいけど、
やっぱり収穫、「食べておいしい!」が
1番じゃないでしょうか?
そこで、前回の「培養土」に引き続き
「土」の話をしたいと思います。
やっぱり「おいしい野菜を食べたいなぁ〜」と思ったら
「土」にこだわることが大切!
そこで、今回第9回は、
家庭菜園で、もっとおいしい野菜を育てるための
「畑の土づくり」についてお話しします。
まずは、基本的なポイントを
おさえましょう。
目次
1:庭の土では野菜が育たない?
野菜に限らず、
「植物がよく育つ土」を作りたいと思ったら、
まず、森の土を思い出して欲しいんです。
森の土をよ〜く観察すると、
小さな塊で構成されていることに気づくと思います。
サラサラでも、コチコチでもない。ふかふかの土です。
落ち葉が腐葉土となり、
動物たちのふんなどの動物性堆肥とも混ざり合っています。
前回の「培養土」でもお話しましたが
森の土のように植物が育つ土の場合、
「団粒構造」がしっかりしています。
なので、水はけも保水性もよく、
空気も栄養もたっぷり含んでいます。
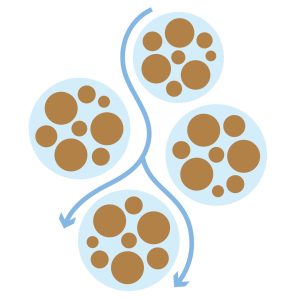

ところが、一般的な庭の土は、
ふかふかの土ではないし、
団粒構造が見当たらない場合がほとんど。
だから、庭の土で家庭菜園を始めるには
土づくりが必要なのです。
2:庭の土から畑の土へ!
これまで1度も畑として使っていない土ならば、
植物性堆肥の腐葉土と、
牛ふんなどの動物性堆肥を1:1に混ぜたものを
庭の土に50%ぐらい混ぜましょう。
※割合は、実際の土の状況によって調整が必要です。


昨年も畑として利用した土ならば
25%ぐらいでいいですよ。
以後、毎年25%ほど、
腐葉土と堆肥のミックスをすき込んで
良い土の状態に育てていきましょう。
3:堆肥の選び方
動物性堆肥には、牛ふんの他に、馬ふんや豚ぷんがあります。
一般的に使いやすいのは、牛ふんだと思いますが
商品によって含まれる牛ふんの量がちがうし、
おがくずやバークが混ざっているものもあるので
容量と価格だけでなく、
袋の裏側をしっかりチェックして
成分を見比べて選んだ方がいいですよ。

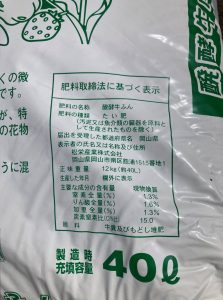
4:化学系肥料の考え方
「長く家庭菜園を楽しみたい!」と思うなら
化学系肥料は最小限に抑えて、
有機質系の腐葉土や堆肥を
しっかり混ぜていくのがオススメです。
なぜなら、化学肥料に頼りすぎると
1年目は、いっぱい収穫できても、
2 年目以降、徐々に土が痩せて 、
収穫量も徐々に減ってしまうからです。
化学肥料は悪いものではありません。
今年、はじめて植えたナスを
それなりにたくさん収穫しようと思えば
化学肥料という選択は非常に有効です。
でも、化学肥料に頼って土づくりをなまけると
土が弱くなってしまいます。
ちなみに私の畑には化学系肥料を使いません。
理由はね、野菜のウマさがちがうから。
ナス1本、キュウリ1本の味に打ち震えますよ(笑)。
5:ふかふかの土に育てよう!
植物がよく育つ「ふかふかの土」に育てるには、
土を耕すと同時に、腐葉土と堆肥を混ぜること。
耕すことで土の中に空気が入るので、
根がよく育つ土になります。
その前の準備として
私は、毎年3月頃、
「苦土石灰(くどせっかい)」を
1平方メートルあたり500gぐらい
畑全体にパラパラとまいています。
苦土石灰には、粉状と粒状のものがありますが、
粒状だと風で飛ばないので使いやすいですよ。
苦土石灰を、ざっくり説明すると
苦土がマグネシウム、石灰がカルシウムです。
マグネシウムは、花や実を育てる栄養素(リン)の
吸収を助けてくれます。
カルシウムは、病気に強い植物を作ってくれます。
さらに、苦土石灰は土のpHも調整してくれるので
苦土石灰をまくことで植物の育ちやすい環境が整う訳です。
土を耕して腐葉土と堆肥を入れる作業は、
種まき、または植え付け前に毎回、行いますが、
苦土石灰は年1回、秋か春のどちらかに行うのが普通です。
また、苦土石灰は植え付け1か月ぐらい前にまくと良いので、
ご自分の育てたい野菜の成育時期と相談しながら
タイミングを調整してくださいね。
6:畝を作ろう!
「畝」は作った方がいいです。
家庭菜園だから必ずではないんだけどね。
畝とは、畑の土を高く盛り上げて作る栽培床のこと。
畝を作ると水はけが良くなるし、
野菜ごとに畝を作ることで
管理しやすくなります。
ちなみに、畝を作ることを「畝立て」と言います。
土の状態や育てる野菜によって
適する畝の高さはちがいます。
特に、水はけが悪い場所は、
ちょっと高めにして水抜けを良くします。
水はけの良い土地を好むサツマイモなんかは
畝の高さ15〜20cmぐらいに高くしますね。
マメ類は強いので畝立てしなくても大丈夫。
ジャガイモ の場合も、土寄せするので
畝立てしにくいのですが、
いずれも、特に水はけが悪い土地であれば
畝立てした方がいいですよ。
その土地の、水はけ状態をしっかり見て、
畝の高さを考えましょう。

7:連作障害を知って植える野菜を選ぼう!
同じ場所で、同じ科の野菜を連続で育てると、
特定の栄養素だけが吸収され続けるので
土の栄養バランスが崩れ、生育に支障が出ます。
このことを「連作障害」と言います。
しっかり土壌改良してあげれば、
大概の場合よくなるのですが、
できれば、ナス科のトマトを植えたなら
次の年はウリ科のキュウリにするとかね、
別の科の植物を植えてあげるのがベストです。
2つの畝を作って交互に入れ替えて植える、
または、ひたすら異なる科の植物を選んで
輪作を続ければ連作障害 になりにくいです。
もちろん、堆肥等をしっかり入れて
土づくりを丹念に行うことでも
連作障害は低減できますよ。
ご自分で判断できなかったら
「去年これを植えたけど、今年これを植えていいですか?」と
お店で相談するといいですよ。
投稿日:2022年7月27日