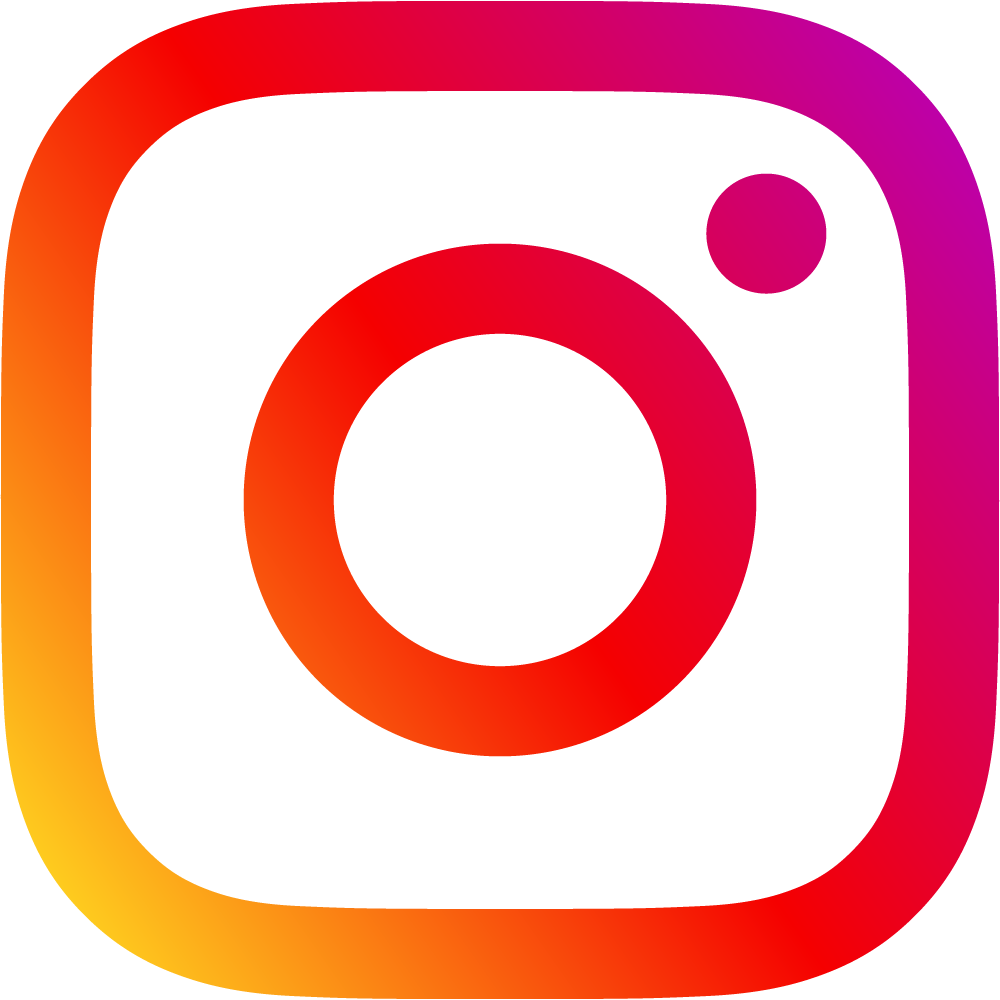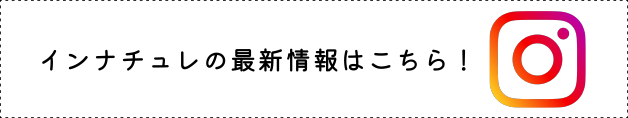第54回オシャレで育てやすい「オリーブ」

みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
私は兵庫県小野市で、ずっと前から
オリーブ栽培を手がけています。
料理ではオリーブのバージンオイルを使うので
岡山県の牛窓オリーブ園まで
油のとり方を勉強に行ったこともあるんですよ。
瀬戸内地域は
オリーブ栽培がとても盛んですよね。
ヨーロッパの地中海地方と
ちょっと似ているのかな。
オリーブと瀬戸内の気候は、
よく合っていると思います。
しかも、大変生命力が強くて育てやすい木なので
園芸初心者の方にも
ぜひ、挑戦してほしいと思います。
ということで、
第54回は「オリーブ」のお話です。
目次
1:オリーブについて
モクセイ科オリーブ属のオリーブは、
地中海沿岸〜中東原産の高木・花木(常緑)です。
明るい日なたを好み、
5〜6月頃に花を咲かせます。
1本の木の花粉だけでは
実がつかない性質があるため、
窓辺の観葉植物みたいに
葉っぱだけ楽しみたい人は1本でもいいけれど
実を収穫したい場合は、
異なる品種の木を2本以上植えたほうが
断然、実つきが良くなります。
異なる品種の方が受粉しやすいのですが
ラベルをよく見て
同じ時期に開花するものを選んでくださいね。
2:品種や大きさを考えて選ぼう
オリーブの品種はとても多いのですが
樹形によって、「直立型」と「開帳型」の
大きく2つに分類されます。
「直立型」は、上に向かってスラッと伸びるタイプ。
マンションのベランダなどでも育てやすいです。

「開帳型」は、枝が横に張り出して伸びるので存在感抜群。
結構、幅を取るけれど、
お庭のシンボルツリーや目隠しにもなります。
果実を収穫しやすいのは、こちらです。


オリーブのラベルには、品種名のほかに
直立型なのか、開帳型なのか、
樹高や果実の用途なども書いてあるので
店頭で、しっかりラベルを確認して
好みの品種を選びましょう。
一方、店頭に並ぶオリーブの木は、
小さいものだと50cm以下からあります。
庭木として、すぐ植えられるのは
2m〜3mぐらいのもの。
もっと大きい木もあるでしょうが、
値段がかなり張ってきます。
オススメは、小さいサイズから育てること。
オリーブの木は、その地域の気候や条件に
合うように成長するので
小さいものを買ったほうがいいと思います。
3:日当たり・水はけ・風通しの良い場所へ
オリーブは日当たりの良い場所、
水はけ・風通しの良い場所が大好きです。
瀬戸内地方ならば1年中、屋外でも大丈夫なので
日当たり・風通しの良い暖かい場所を選んで
植えてあげましょう。
その場合、オリーブは弱アルカリが好きなので
植えつけの2週間前に苦土石灰をまいて
弱アルカリの環境を作ってあげると
生育が良くなりますよ。

作業の手間を考えると
植える予定の場所に
深さ・直径50cmの穴を掘り、
堆肥や腐葉土、苦土石灰を
加えて用土を作っておくと良いでしょう。
水はけが心配な場合は、
細かい軽石などをしっかり混ぜて
水はけを良くするといいですよ。

鉢植えで育てる場合、
ベランダや屋内でも育てられますが
冬は10℃以下で管理しましょう。
理由は、冬の寒さに当てないと
花や果実をつけないから。
そのため、冬の暖かい日には
外の風に当ててあげましょう。
雨に当ててもいいし
水で葉っぱの汚れを取ってあげるのも
いいと思います。
もちろん、すごく寒い場合は、
部屋の中の方がいいと思いますよ。
氷点下に下がるところや
寒風がずっと当たり続けるところも
避けてあげましょう。
4:若木には支柱を立てよう
風で枝が折れやすいので
若木には支柱を立てた方がいいです。
とくに横に広がるタイプの場合、
品種によっては、かなり
枝が柔らかいです。
支柱を立てる場合のベストは3本。
3本の支柱で3方向から支える八掛け支柱、
または鳥居型に組むとがっちりします。

5:水やり・施肥で気をつけること
庭植えの場合は、
根が張るまではしっかりと水を与えますが
そのあとは基本的に水やり不要です。
鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら
水をたっぷり与えます。
だけど、オリーブは過湿の状態が
あまり好きではないので
その点だけ注意してくださいね。
肥料は
植えつけの2週間後に、
粒状の緩効性化成肥料を適量まきます。

その後、2月と10月に各1回。
有機質肥料、または
即効性化成肥料を適量与えます。
2月と10月の両方でもいいし、
花芽分化を促す2月だけでもいいと思います。
剪定時期も2月〜3月なので
剪定するときに
肥料を与えるといいんじゃないかな。


長く植えている場合は、毎年2月頃、
根っこを切るようにして
直径20cm×深さ20cmの穴を
2か所ぐらい掘って
そこに堆肥と、元の掘り上げた土を
混ぜたものを入れてあげると
ちょっと元気になるでしょう。
鉢で育てている人は
液肥を使ってもいいと思いますよ。
6:人工受粉のコツ
果実をたくさんつけたいならば、
人工受粉を検討しましょう。
また、同時にお花が咲いてくれれば
虫や風が交配してくれますが
花の時期がずれちゃう場合は、
当然、実つきが悪くなるので
そういう場合は人工受粉がオススメです。
先に咲いた花の花粉をとって
ジッパー式の保存袋に入れて
密閉保存しておきます。
その際、カビが生えないように
お菓子の乾燥剤でも何でもいいので
乾燥剤と一緒に入れて
冷蔵庫に保管しておけば
1〜2か月間はもちますよ。
そして、次の花が咲いたら
綿棒などでトントンと花粉をつけてあげましょう。
7:使い方によって収穫時期を変えよう
オリーブの果実を塩漬けにする場合は
9月以降の未熟な果実を収穫して使います。
オイルをしぼる場合は
完熟する12月頃に収穫しますが
かなり大量の果実が必要となります。
8:増やす場合はさし木が一般的
オリーブは、果実からタネをとって
栽培することもできますが
通常は、さし木で増やします。
さし木をする時期は休眠枝挿しは2月から3月、緑枝挿しは6月がベスト。
土にさしてから約2か月で発根します。
発根までの期間が長いので
発根剤をつけた方がいいでしょう。

さし木をする土は
さし木用の土で大丈夫ですが
さし木用の土に、パーライトを2〜3割混ぜると
発根状態がすごく良くなって、
いい根っこがたくさん出てきますよ。


9:剪定で樹高を調整しよう
オリーブの木はまったく剪定しないと
6mくらいまで
大きくなってしまいます。
そうならないように、
毎年、先端を剪定します。
剪定は、2月の後半から3月くらいにかけての
早春におこないます。
ここで、気をつけたいのは
オリーブは去年伸びた枝に
花が咲く「旧枝咲き」という
性格をもっていること。
あまり深く切り過ぎると
花が咲かなくなり
実の数も減ってしまうので
樹形を維持するよう
先端を切る剪定をします。
樹高1m50cmくらいの
持ち運び可能なサイズから
大きくならないように剪定して
部屋の窓辺に置いておくとかわいいし、
管理もやりやすいですよ。
それでも、大きくなってくると
ちょっと大変なので
数年に1回、強めに剪定したり、
木の広がりを抑え、
不要な枝を間引く「すかし剪定」を
おこなうといいですよ。
10:病害虫対策
オリーブの木は生命力が強いので、
病害虫の被害にあっても
ごく初期の小さな変化に気づくことで
オリーブの木を助けることができます。
だから、1週間に1回は
木の様子をしっかりチェックしましょう。
オリーブには、人を刺すような虫は寄って来ないんだけど
カミキリムシ、オリーブアナアキゾウムシ、
ハマキムシなど
幹や枝葉を食べ荒らす系の害虫に
注意が必要です。
とくに、オリーブ最大の敵は
カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)。
幹に穴を開けて中に入って
枯れるまで食べ尽くします。
見つけるポイントは
幹から出てくるおがくず。
カミキリムシが木の中に入ると、
おがくずが出てくるので、発見したらすぐに
穴をちょっとほじくってね、
ノズルの付いた園芸用キンチョールを
シューッ!!!!!と数秒かけます。
見つけたら、すぐやる。
これが大事。
じゃないと、食べ尽くされちゃいます。

そのほか、清耕栽培(草を生やさない栽培方法のこと)といって
なるべく草を生やさないようにして
幹をむき出しにしておくことも
予防につながります。
もしも、カミキリムシに食べ荒らされても、
スカスカになった部分をすべて削り取って
カルスメイト(癒合剤)を塗り固めて
適切に処理すれば
生き返って元気になることが多いけれど
大がかりな治療になるから
できれば初期段階で見つけてあげてほしいな。
ハマキムシは葉っぱを丸めて
その中にすみつくんだよね。
ハマキムシは、オリーブの枝の先端の
柔らかい葉を好んで食べるので
5〜6月の新緑の頃、
くるんと巻いた葉っぱを見つけたら
虫がいないか、注意して見てください。
見つけたら捕殺、または薬剤散布で
即対応しましょう。
一方、病気になることは少ないんですが
害虫に食べられた部分に
糸状菌が侵入することで
病気に感染することがあります。
さらに、木が弱ると
キノコができちゃう。
こうなると、枝の先端から枯れていくので
発症した枝を見つけたら
早め、早めに取り除きましょう。
とくに梅雨時に多発するので
注意しましょう。
第55回目は、チューリップについてお話しします。
11月13日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!
投稿日:2024年10月23日