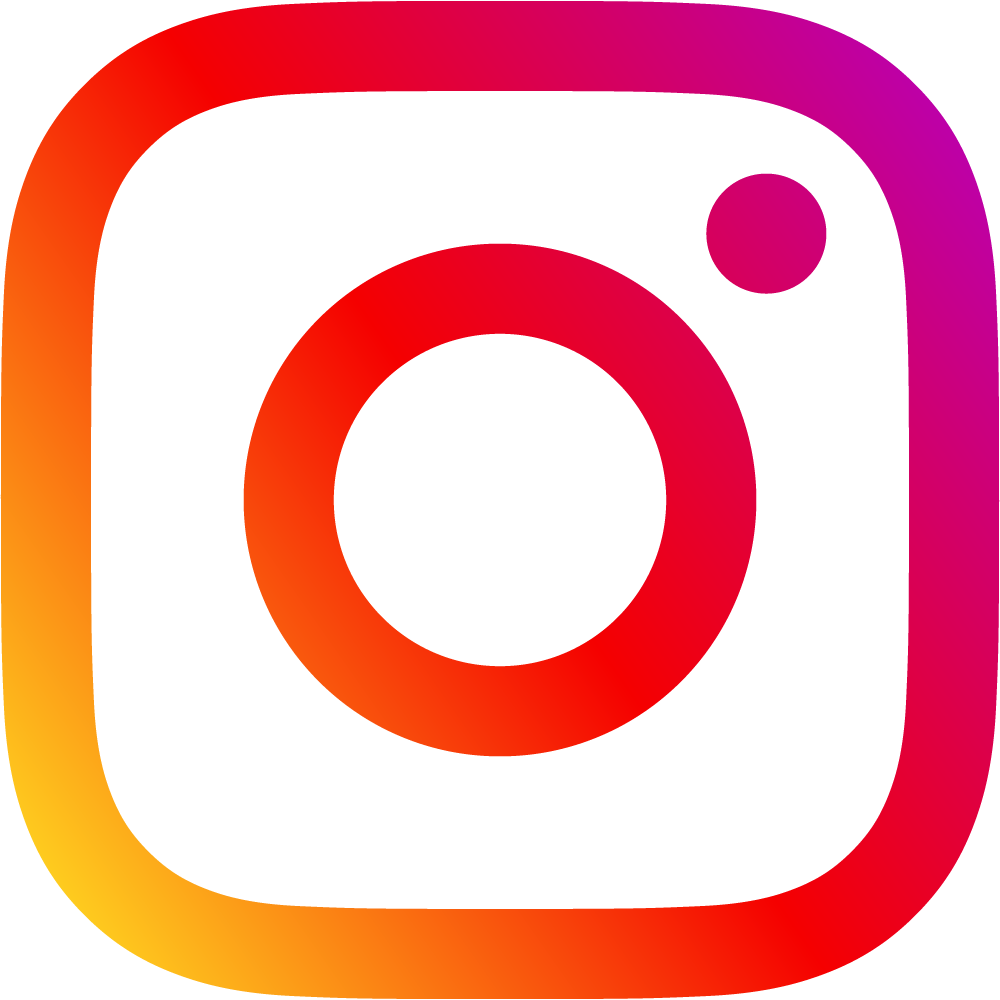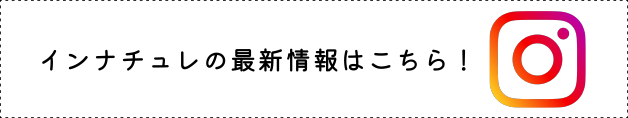第73回花壇の「土づくり」は10月に!

みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
ようやく猛暑も落ち着いて
ずいぶん過ごしやすくなりました。
10月は、秋冬から来春に向けての
花壇の準備にぴったりの季節です。
たとえば、これから植える宿根草には
クリスマスローズやアスチルベ、
ホスタ、ヒューケラ、アジュガ…、
いろいろありますね。
チューリップやムスカリなどの球根類と合わせるのも
いいですよね。
もちろん、パンジー、ビオラといった
冬を彩る一年草もたくさんあります。


「どんなお庭にしようかなぁ」
と夢や憧れをイメージしながら
少しずつでもいいので
お庭の花壇の「土づくり」に
トライしてみませんか。
ということで、第73回は、
花壇の「土づくり」についてお話します。
目次
1:ふかふかの土をめざそう!
植物を元気に育てるには
根を育てることがとても大切です。
根を育てるには、水と養分と空気が必要。
そのために、水はけ・水もちがよくて、
栄養と空気を適度に含んだ土を
つくってあげることが
私たち人間の役目なんですね。
本を読むと
「水はけがよく、水もちがよい土は
団粒構造をしています」みたいに
書かれていると思うんですが
「団粒構造の土」って、何だかわかりにくいでしょう?
だから私は「ふかふかの土」と表現しています。
水分と栄養を施しても
土の中に空気がなかったら植物は育ちません。
ふかふか=空気が入っている状態なので
「ふかふかの土」の手触りをめざして
土づくりを一緒にがんばりましょう!
2:土づくりの前に!
「ふかふかの土」をつくる前に
10月の花壇には、
夏の植物が、まだ残っていると思いますので、
まず、それらのお片づけをしましょう。
ひまわりとか、マリーゴールドとか
夏から初秋にかけて花壇を彩ってくれた植物たちを
ハサミでチョキチョキチョキっと
5cmぐらいの大きさに刻んでから
土の中にすき込んじゃう。
その土地にあった有機物を
その土地に戻してあげる作業をすることで
この後の花壇の大事な肥料になりますよ。
あと、刈り取った雑草も小さく刻んで
これも土にすき込みましょう。
根っこは取り除かなくてもいいですからね。
ただし、雑草の種には気をつけてください。
土にすき込むのは種の付いていない部分。
種の付いた部分は燃えるゴミに出した方がいいですよ。
3:植物は弱酸性の土が好き!
次は、土の酸度調整です。
日本の土は、酸性雨などの影響によって
酸性方向に傾きがちなのです。
だけど、ほとんどの植物は弱酸性の土が好きで、
土が酸性に傾くと根の先が焼けてしまって
栄養や水分を吸収できなくなってしまいます。
何もしないと土は酸性のままになるので
ちょっと良くないですよね。
ということで
アルカリ性の資材を加えて
土を弱酸性に調整してあげます。
ここで作業に入る前に
できれば酸度をはかってみましょう。
園芸家の私たちはpHメーターを使いますが
ひとつ1〜2万円ぐらいするので、
リトマス試験紙みたいな、酸度を調べられる測定用紙が
ホームセンターなどでお手頃な価格で
手に入ると思いますのでこれで、
お庭の土の酸度を調べてみてください。


理想は弱酸性。pH5.5〜6くらいです。
花壇の土は1年に1回は
酸度調整した方がいいので
春か秋の植え替え時に酸度をはかって
調整するといいですよ。
酸性に傾いた土を弱酸性にするには
通常、苦土石灰を適量まいて、よく撹拌します。
米のもみ殻を蒸し焼きにして炭化させた
もみ殻くん炭を使ってもいいですよ。
ただし、くん炭は強いアルカリ性なので
使う量は、土の量の5%以下にしましょう。
それ以上入れちゃダメです。
5%以上入れちゃうと
アルカリ性が強くなり過ぎて
根が溶けちゃうんでね。

もし、苦土石灰をまいた後に
くん炭を加えるなら2〜3%くらいに
抑えた方がいいです。
くん炭は少なめにね。

気をつけたいのは
酸性の土が好きな植物もいること。
ツツジの仲間やブルーベリー、フジ、サツキなどは
酸性の土の方が好きだということも覚えておいてください。
植物の種類によって最適な土は異なるので、
そこを勉強するのも大事ですよ。
4:堆肥で土に栄養補給!
苦土石灰をまいた後、
1週間以上、そのままにしておいてから
堆肥を混ぜてあげましょう。
私は完全発酵の腐葉土を使っていますが
一般的には、牛ふん堆肥やバーク堆肥が
よく使われますね。
いずれにしても、よく発酵したものを
使ってくださいね。



5:ブレンドで10年もつ土に!
冬の花壇を彩るパンジー/ビオラなどの1年草の場合は
花を楽しめるのが初夏までだから、
およそ半年先までのことを考えればいいので
土の質に深くこだわる必要はないのですが
宿根草の場合、その場所に根をおろしちゃうので
10年たってもその場所が快適であるように
硬質赤玉土や硬質鹿沼土を使うことを
オススメしています。


硬質の土は、1回焼き固めているので
粒が硬く、長い間、壊れないから
水はけも、空気の通りもよくなるんですね。
値段は、硬質のほうが1.5倍くらい高価ですが
硬質でなければ土の粒が粉々に崩れて
泥になっちゃうんですね。
すると、通気性も排水性も悪くなるので
根が傷んで宿根草がダメになってしまうんですよ。
宿根草は一度植えると
10年くらい植えっぱなしになるので
宿根草には硬質の土を使った方がいいです。
私の実感では
値段が1.5倍でも、持ちは10倍だと思います。
宿根草は、最初の植え時が肝心。
その後の手間をラクにできるように
最初の資材は、いいものを使いましょう。
もしも、市販の安価な草花用培養土を使うならば
それに硬質赤玉土を2割くらいプラスして、
さらにパーライトを5%ぐらい加えるといいですよ。
パーライトも粒が潰れないので宿根草に有効です。
ここに完熟の腐葉土を2割ぐらい加えれば、もっといいですね。
腐葉土は、より細かく分解されたものであれば、なおいいです。
ブレンドの割合は、植物によって若干異なりますが、
約半分ぐらい足りないものを加えて
アレンジする方法もありますよ。
これらの硬質赤玉土、パーライトなどは
発酵しないので植え付けの直前に加えても大丈夫です。

6:秋植えの球根類も同様に
秋植えの球根類を植える土も、
宿根草と同じ考え方で大丈夫ですよ。
例えばチューリップを翌年春に咲かせた後、
抜いてしまうなら1年草の考え方でいいです。
私みたいに1つのチューリップを
10年〜15年も咲かせたいと思ったら
やっぱり土にこだわらないといけないんですね。
年々、だんだん土が締まってきちゃうので
硬質赤玉土や硬質鹿沼土、パーライトなど
潰れにくい土を使った方が絶対いいです。
ときどき質問で
「スイセンの花の数がどんどん減っている」
とお聞きするんですが、それは、そういうことなんですね。
植えつけた時とは空気の通りがまったく変わっちゃって
土が粉々になるというか、泥みたいになっちゃう。
すると、花が上がらなくなってきます。
ヒヤシンスやラナンキュラスラックス、ムスカリなど
秋植えの球根類も、みんな同様ですよ。
10月は、まだ暑い日もあるけど、
土づくりをがんばると、きっと春に
いい景色が見られますよ。
7:最近の気温について考えること
今年、注意したいのは「気温」ですね。
昨年の10月下旬にチューリップの球根講座を
開催したんですけども
暑くて植えられる状況じゃなかったので
11月上旬にスケジュールを変更させていただいたんですね。
ちょっと前まで、どの本にも
秋の球根を植えるのは10月って
書いてあったと思うんですが、
暑かったら11月でもいいですよ。
気温がしっかり下がったかどうかを
見定めて植えないと
球根が土の中で腐っちゃうので気をつけてください。
私が、球根の植えどきを決めるのに
目安にしているのは「落葉」です。
バラの葉やアジサイの葉が黄色くなってきたら、
または落葉したら植えつける、としています。
それでもね、
昨冬はバラも1月くらいまで葉っぱが落ちなかったので
神奈川の方では強制落葉させました。
8:おまけ:プランターの土を再生するには
プランターで使った培養土については
再生して、再び使っています。
まず、一番粗いメッシュのふるいで振るって、
土の中に混ざっている根っこや葉っぱなどを取り除きます。
次は一番細かいメッシュのふるいで振るいます。
目が一番粗いのと一番細かいものの
中間の大きさの土だけを取り出して、
ここに赤玉土やパーライトを混ぜて
ふかふかの土になるようにします。
1週間ぐらい様子を見て
ふかふかの手触りを確かめてから
使ってくださいね。
このときに、カルスNC-Rなどの再生剤を使うと
再生までの時間が早くなります。
説明書きをしっかり読んで正しい方法で
使ってみるといいと思いますよ。
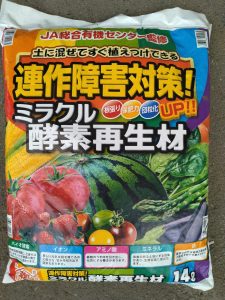

第74回目は、ソラマメについてお話しします。
10月22日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!
投稿日:2025年10月8日