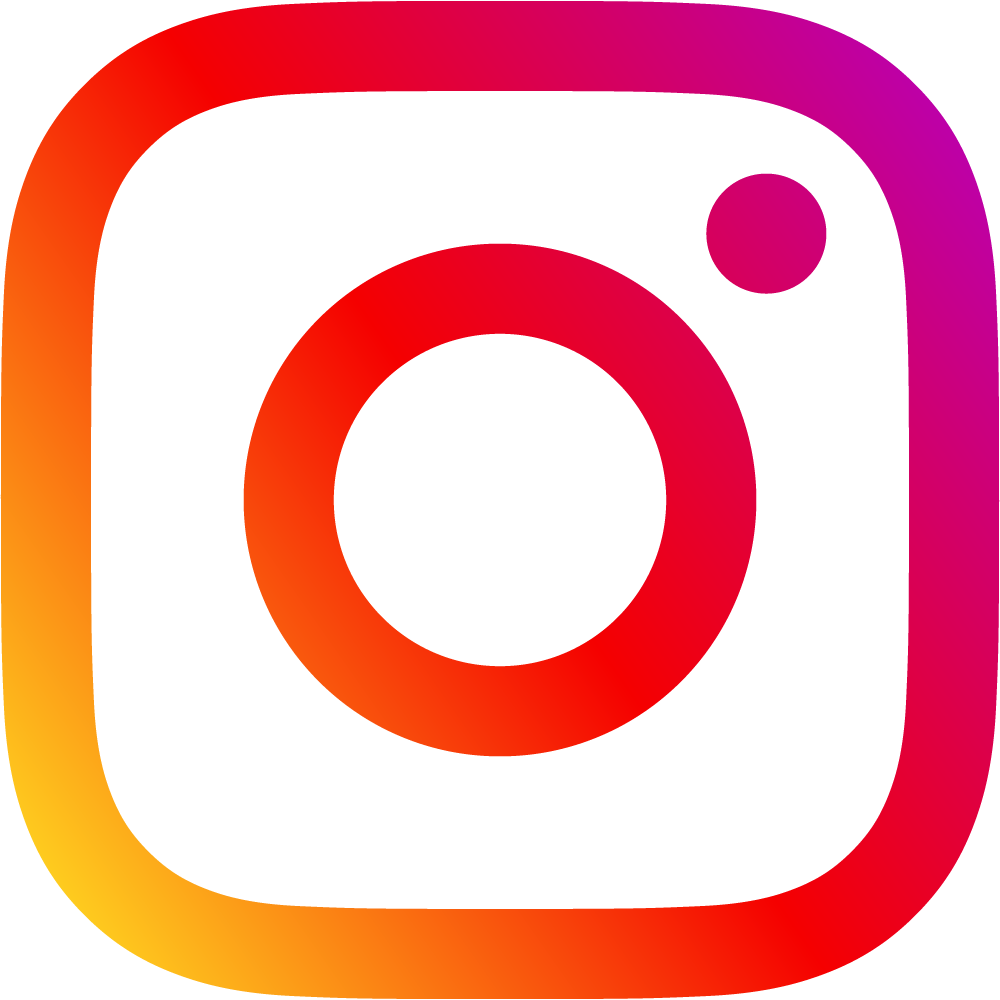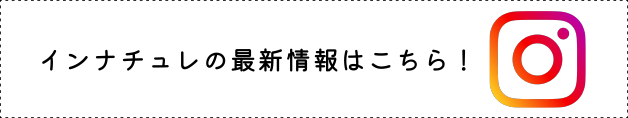第68回草は、ともだち!「自然栽培(不耕起栽培)」

みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
いよいよ夏本番ですね。
夏野菜の収穫を楽しむ一方、
畑の「草」と戦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、いま、耕さない・草を抜かない
自然栽培「不耕起栽培」に取り組んでいます。
草と戦わず、草と共存しながら
作物の力を引き出す環境をつくる農法なのですが、
年をとってもラクに家庭菜園を続けるためにも役立つ農法だと思います。
興味のある方は、ぜひ、じっくり読んでみてくださいね。
ということで、第68回は「自然栽培(不耕起栽培)」について、
「草」についての私の考えをお話します。
目次
1:不耕起栽培のメリットとは
私が取り組んでいる自然栽培「不耕起栽培」は
「自然の力を遺憾なく引き出す永続的な農業方式」です。
自然の力を利用して、
作物の力を引き出す環境をつくろうと考え抜いたら
「耕さない、草を抜かない」やり方にたどり着きました。
体力的な負担が軽くなるので
長くラクに続けられると思いますよ。
また、不耕起栽培をすると
枯葉や草を集めて燃やすことをせずに、
枯葉や草を腐葉土化して、そのまま畑にすき込んで
堆肥として使うのでCO2対策にもなります。
水やりも、最初の植え付けのときだけは
しっかり水分を与えますが、
異常な日照りが続く場合を除けば
ほとんど必要ありませんからラクになりますよ。
2:不耕起栽培にぴったりの野菜
昨年、「自然栽培」についてお話したときにも
レタスを虫除けがわりに使っている事例を紹介しました。
同様に、不耕起栽培とレタスの相性もバッチリです。
しかも、不耕起栽培でレタスを育てると、
1年草のレタスが宿根するんですよ!
春から育てたレタスを収穫したら、根っこを抜かずに
切り口が乾いてから土をかけておくんです。
土のかわりに稲わらでもいいです。
するとね、
そのまま宿根するんです。
不耕起栽培だと耕す必要がないから、
根っこも抜かなくていいんです。
そのまま植えっぱなしで冬を越すと
軽井沢だと4月の半ばぐらいから新芽が吹き出します。
軽井沢の冬は-15℃まで気温が下がるのですが、
それでもレタスの根っこは耐えられるんですよ。
そして、5月の連休ぐらいには収穫が始まります。
中国地域だと、もっと早いかもしれないね。
切り株の脇からレタスがいっぱい芽吹いてきて、
そうだな、1つの株に5〜6個ついてるかな。
面白いでしょう?
しかも、宿根レタスは、根っこがしっかりしているから
タネや苗から育てるより早い時期に収穫できます。
スーパーや市場での値段が高い時期に
収穫できるのはうれしいですよね。
レタス以外の野菜では、
カボチャ、秋ナス、トウガラシもオススメです。
ちなみに、トウガラシを自然栽培で育てると辛さが増すので、
辛いもの好きな人には最高ですけど
香辛料に弱い方は気をつけてくださいね。
その他だと、ニンニクもいいですね。
ニンニクを畝の中央に並べて植え、
その両脇で他の野菜を育てたら、野菜の病気除けにもなりますよ。

夏植えのジャガイモや
白菜、小松菜、水菜、春菊、ダイコン、ニンジンといった
鍋に入れるような野菜もいいですね。


自然栽培でニンジンをつくると
むか〜しのニンジンの匂いがしますよ。味が濃い。
しかも、自然栽培だと農薬を使わないから
葉っぱも全部食べられます。
ニンジンの葉っぱって、すごく美味しいんですよ。

人参種袋タマネギやニンニクは、化学肥料を使わない自然栽培だと
本来の大きさに育つので小さくなります。
化学肥料を使って育てた場合のサイズの半分ぐらいですね。
でも、味は、本当に濃いです。
また、大きなタマネギは、
保存しても夏にはドロッと溶けてしまうけれど、
自然栽培のタマネギは実がしっかり締まっているので
秋まで保存しやすいです。

なお、ジャガイモや、葉物・根菜類など
アルカリ性土壌を好む野菜を栽培するときには
カリウムを豊富に含む
市販の草木灰を堆肥や追肥に使用すると
生育を助けてくれますよ。

また、マメを育てると土に栄養補給できるので、
大豆や枝豆、インゲンなどのマメ類を育てるのもいいと思います。
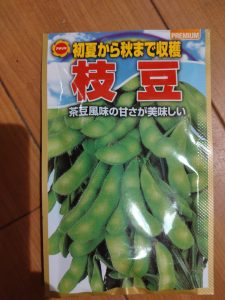

3:雑草をきわめよう!
自然栽培をするなら、「草は、ともだち」。
雑草を大切にしましょう。
雑草について勉強すればするほど
いろんなこと、自然のつながりが見えてきて、
自然も、農業も、もっと面白くなってきます。
「あぁ、だから、ここに生えてるんだ」って
植物の気持ちが分かるようにもなります。
お子さんやお孫さんと一緒に、畑の雑草の夏休み研究をしてみるのも
きっと楽しいと思いますよ。
とくに、カラスノエンドウなどマメ科の雑草はスグレもの。
花をつけたら上部をカットし、
そのまま根元に置いておきましょう。
そうするとマメ科の雑草が
大気中の窒素を植物が利用できるように変換(窒素固定)して、
土に栄養を蓄えてくれます。
-300x225.jpg)
イネ科の雑草も、抜いちゃダメですよ。
イネ科の雑草は、かたい土を耕すために根を張ってくれています。
新しい根を周りに広げて、どんどん耕し、
土をほぐして中に空気を入れてくれるんです。
だから、根元から5 cmぐらい残してカットします。
先ほどのカラスノエンドウは地面ギリギリで切って、
根っこだけ残して上の葉っぱをその場所に伏せるんですが、
イネ科の雑草を一番下でカットしちゃうと
成長点を切ることになり、死んでしまうので、
生かすために5cmぐらい残してください。
よく見かけるイネ科の雑草というと、
ススキ、メヒシバ、「猫じゃらし」と呼ばれるエノコログサなど。


こういったイネ科の雑草が畑に生えていたら
「ラッキー」と思って
5 cmくらい残し、切った葉っぱは、その場所に置きましょう。
イネ科の草は「草マルチ」としても、そのまま使えます。
雑草って、それぞれ住み分けしているんですよね。
荒れ地にはスギナやチガヤが出てきます。
荒れてはいないけれど、かたい土地にはイネ科の雑草が出てきます。
やや日陰で酸性の土地にはドクダミが出ます。
スギナやドクダミが出てきたら、
野菜栽培には良くない土壌だと思っていただいていいでしょう。
だけど、その雑草たちは、その土地をつくり直すために出てくれています。
ドクダミとスギナは、両方とも荒れ地の成分を吸収し
自分の体を使って土の栄養となる成分をつくりあげ、
自分は枯れて、そこの土を耕し肥沃にしてくれるんです。
スギナもドクダミも嫌われているけれど、
実は素晴らしい雑草です。
ドクダミ茶も、スギナ茶も、健康茶として
大昔から飲まれているでしょう?
素晴らしい働きをしてくれているんですよ。
4:最初の2年間は土づくり
自然栽培の1年目と2年目は
「土づくり」です。
まず、1年目は、
これまで、どういう畑だったのかを見極める時間。
前年は何の作物を育てたのか、
農薬を使ったかどうかが分かるといいですね。
もし、農薬を使っていたら、
半年から1年かけて土づくりを頑張りましょう。
枯葉や雑草を乾燥させたものなど、自然の堆肥をたくさん投入して
土をしっかり耕します。
枯葉や雑草を土中にそのまますき込むと、
気温にもよるんですけど、
分解されるのに最低7〜8カ月かかるんですよ。
だから、すき込んでから1年くらい放っておく、
翌年から作物を育てるといいと思いますが、
すぐに苗を植えたいのであれば、
枯葉や雑草をそのまますきこむのではなく、
別の場所で腐葉土に変えてしまってから
畑に入れてあげると良いと思います。
そして、2年目の春から試験的に、
何か作物を栽培してみましょう。
そして、3年目から完全な不耕起栽培に取り組みます。
5:自然栽培用の苗やタネ
ホームセンターでは自然栽培用の野菜苗やタネは、
ほとんど取り扱われていないと思いますが、
ネットショップなどでは入手可能です。
または、自分でタネを採取して、
農薬成分をできるだけ少なくして発芽させ、
苗をつくってみるといいでしょう。
農薬に頼らずに育てた苗を植えると、
独特な「えぐみ」が強くなり
虫やカビ菌などの被害を抑えてくれますよ。
第69回目は、ひまわりについてお話しします。
8月6日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!
投稿日:2025年7月9日