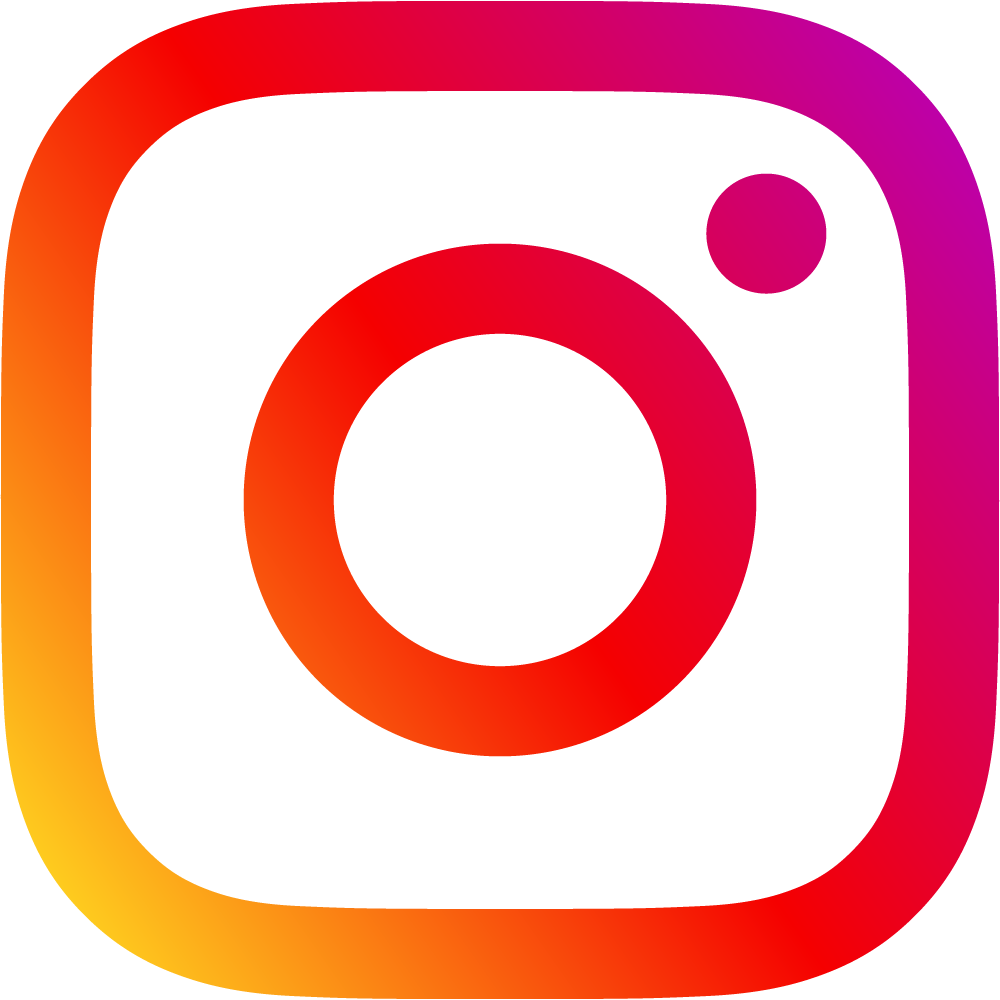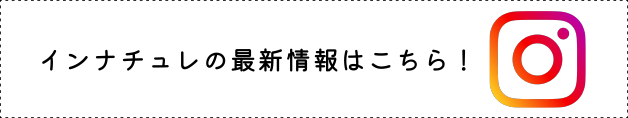第64回猛暑に負けない夏野菜「オクラ」

みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
今年の夏も暑くなりそうですね。
私は猛暑に負けないカラダをつくるために
“ネバネバ野菜” をたくさん食べるようにしています。
なので、オクラは絶対、夏に欠かせない食材なんですね。
さっと茹でるだけでおいしいし、
納豆に混ぜてもいいし。
オクラは失敗が少ないので
この夏、初めて家庭菜園にチャレンジする方にも
オススメですよ。
ということで、第64回は、
「オクラ」についてお話します。

目次
1:オクラとは
アオイ科アオイ属のオクラは
原産地がアフリカ!
すなわち、暑さにも乾燥にも強いので
最近の猛暑でも育てやすい夏野菜なんですね。
花も魅力的ですよ。
レモンイエローの大輪の花がとてもキレイです。
食べるのは若いサヤの部分。
栄養面も、とても優秀で
あのネバネバ成分のもとになる食物繊維をはじめ、
ビタミンB1・B2・C、カロテン、カルシウム、
リン、鉄、カリウムなどを多く含んでいます。
しかも、サラダだけでなく煮物や、あえ物、天ぷら、炒め物など
いろんな料理に使えるところもうれしいですよね。
生育適温は20℃〜30℃です。
暑さに強いぶん、寒さには弱いので
地温が十分に上がらないうちに苗を植えてしまうと
枯れてしまうことがありますが
5月中旬以降であれば、寒さの心配はないでしょう。
2:育てやすい品種が増えています
オクラのサヤの形は五角形が主流ですが、
丸や八角形もありますよね。
丸サヤで有名なのは、沖縄の島オクラとかね。
赤とか黄色とか、色のついた品種もあります。
最近は、種苗メーカーによって
育てやすく改良された品種が増えているので
バラエティに飛んでいます。


私は、多角形のオクラが好きなんです。
若いウチに収穫して食べると美味しいんですよ。
ちょっと時間が経つと繊維だらけになっちゃうんで
できるだけ早く収穫しなきゃいけないんですが。
丸オクラの方が比較的、大きくなっても柔らかいですけど、
「比較的」であって、やっぱり柔らかいうちに
収穫して食べる方がオススメです。
3:水はけの良い場所に苗を植え付けよう
オクラを育てる場所は
日当たりが良く、肥沃で水はけの良いところがいいですね。
土質は特に選ばないんですが、
酸性の土壌は適さないので
定植する場所を決めたら
1カ月前から土づくりをしたいところ。
まず、堆肥をすきこみ、
堆肥が発酵するよう、よく混ぜます。
そして、定植の2週間前に苦土石灰を散布して耕す。


そして、田んぼの跡など、水はけが特に悪い場所の場合は
15cmくらいの高さの畝を立てますね。
普通の畑、水はけの良い畑なら10 cm以下でも、
ヒラでも大丈夫です。
気をつけたいのは気温です。
生育適温は、日中の気温が20〜30℃。
5月の連休明けであれば
かなり暑くなっていると思うので
心配なく定植できると思いますよ。
オクラは、ポット1つに大体2〜3本の苗が入ってると思います。
苗を植える場合は、1つのポットをそのまま植えていいです。
苗をばらして植えると、あんまりうまくいかないので
そのまま植えます。
1つのポットに2〜3本の苗が束になっているので
その束の隣に、40cmぐらいあけて別のポット苗を植える。
広がりますので
草丈が1 mを超えて、2mぐらいに育つこともあるので
小さな菜園の場合は
他の野菜が日陰にならないように
植え付け場所に注意しましょう。
畑の北側に植えるとかね。
オクラは茎がものすごく太くなって、
最終的にはノコギリで切るぐらいの太さになるので
畑の場合、通常、支柱は立てませんが
日当たりが悪く、ひょろひょろしてる場合は
支柱を立てた方がいいですね。
01-225x300.jpg)
植木鉢やプランターで育てる場合、
オクラは直根、つまり根っこが真っ直ぐ生えるため、
深めのものを選んでください。
用土は、野菜用の市販の培養土でOKです。
プランターで栽培する場合は、支柱をした方が良いでしょう。


4:肥料のやり過ぎに注意
オクラは肥料をよく吸収するので、
窒素系が多いと生育旺盛になってしまい
葉っぱばかり大きくなってね、
花つきが悪くなったり、実つきが悪くなったりするので
肥料は、ほどよい量を加減する必要があります。
畑に、どのくらいの肥料成分が入っているかわからないと
なかなか難しいので、
たとえば、初年度はお試しとして無肥料で栽培し、
どういうオクラが実るかを見て
翌年から肥料を考える。
または、種苗会社などのマニュアルを見て
規定の緩効性化成肥料と量で栽培してみるのもいいでしょう。
その場合、最初の肥料を施したあと、
葉の色や実の状態をよく見て、
肥料を追加するかしないか、1カ月後に考えるようにしてください。
1カ月は、様子を見る。

気をつけたいのは収穫期にあたる夏場の追肥。
真夏の暑さで化成肥料が急に溶ける場合があるので、
一度にドンと施すんじゃなくて、
少なめの量をパラパラとまくなど
様子を見ながら追肥するようにしましょう。
もしも、葉の色が薄くなっていたら、
即効性がある液肥を与えてもいいと思います。
とにかく1年目は観察が大事。
その1年目の観察に基づいて
2年目から肥料の量を加減していく。
これが畑の考え方だと、私は思います。
植木鉢やプランターで育てる場合は
培養土の中に肥料成分が入っているので
成長の様子を見ながら追肥を考えましょう。
水がわりに液肥を使ってもいいと思いますよ。

5:水やりは雨におまかせ
オクラは、もともとアフリカ原産なので乾燥に強いです。
ですから、畑で育てる場合は、
よっぽどの日照り続きでない限り、通常は雨だけで十分です。
しかも、オクラの根っこは直根なんで
地下深くまで伸びてるんですよ。
表土が乾いていても意外と強いです。
ただし、植木鉢やプランターで育てている場合は
表面の土が乾いたら
しっかり水を与えてあげてくださいね。
あまり乾燥気味の状態が続くと
実が硬くなっちゃいますよ。
6:葉摘みをしておいしく育てよう!
おいしいオクラを育てるには
「葉摘み(摘葉)」が大切です。
風通しや日当たりを良くして
病害虫も防げるので、ぜひ葉摘みをしましょう。
やり方は簡単。
収穫したサヤの付け根にある葉っぱと、
その下の葉っぱ4〜5枚を残して
そこから下の葉っぱを全部むしり取るだけ。
また、下の方から脇芽が出てくるんで
その芽も一緒に取ってもらう。
次の実を収穫したら、
同じように下4〜5枚の葉っぱを残して
葉摘みして、ついでに脇芽も取る。
実を収穫するたびに、葉と脇芽を摘むので、
下から1 mぐらいは棒状になります。
これを続けると光合成がうまくいって
立派でおいしいオクラになりますよ。
7:収穫はできるだけ早めに
品種によってスピードが異なるんですが
オクラの成長は意外とはやいです。
花は1日花なのでスグ落ちてサヤができます。
ちょっと油断するとね、
そのサヤが結構な大きさになる。
育ち過ぎると噛み切れないくらい硬くなります。
タネもコロッコロに大きくなる。
なので、オクラはできるだけ
若いサヤを収穫しましょう。
「食べ時だ」と思ったらスグとること。
雨が降ると、ぐんと伸びますから
花が咲いたら、ちょくちょく見に行って
収穫した方がいいですね。
ちなみに、つぼみを収穫して天ぷらにしても美味しいですよ。
ただし、多角形の品種には
実のところにトゲがいっぱいあるので注意してくださいね。

8:気をつけたい害虫について
オクラの生育が悪いなと思ったら
病気よりも害虫被害を考えた方がいいでしょうね。
代表的な害虫はネコブセンチュウとハスモンヨトウ。
根っこにコブができていたらネコブセンチュウに
寄生されて生育が抑制されていると思われます。
ヨトウムシは夜に活動して葉っぱを食べちゃう。
どちらも土の中にいる虫で
化学農薬を使って殺虫する方法があるんだけど
食べる野菜を育てるのに、あんまりやりたくないんだよね。
ネコブセンチュウが発生している場合は
早めに撤去して土の太陽熱消毒など、対策を行いましょう。
ハスモンヨトウは、夜に懐中電灯を持って畑に行き、
見つけたら捕殺、これが一番いいんだけど
捕殺しきれなかったら、
オルトランなどの浸透移行性殺虫剤を使うことになります。
もしも使用する場合は説明書をよく読んで
「収穫の何日前までに使って」という用法を
きちんと守って使ってください。
そのほか、ハマキムシという、
ガの幼虫の被害もありますね。
葉っぱを巻き込むように丸くしてね、
その中で生活するイモムシみたいな虫で
コレがいると葉っぱが光合成できなくなって
生育が悪くなるんですよ。
葉っぱが、くるんと巻いていたら
その中にいるので、葉っぱごと切って駆除しましょう。
最近は、カメムシの被害も多いです。
実が食べられていたらカメムシでしょうね。
カメムシにチュッ、チュッて吸われちゃうと
その部分が曲がっちゃうんです。
カメムシ被害にあっていたら頑張って捕殺しましょう。
私は、ガムテープを使っています。
なにしろ一発で仕留めないと臭いので
カメムシをピタッとくっつけて丸めてポン、です。
9:毎年、オクラを育てたいと思ったら
オクラは連作障害が出やすく、
連作をするとネコブセンチュウの発生も増えます。
なので、毎年オクラを育てる場合は、
畑の土を土壌改良して
もう一回よみがえらせるような土づくりをする、
または連作障害にならないよう
後作でアオイ科以外の科の植物を植えるようにしましょう。
第65回目は、バラについてお話しします。
5月28日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!
投稿日:2025年5月14日