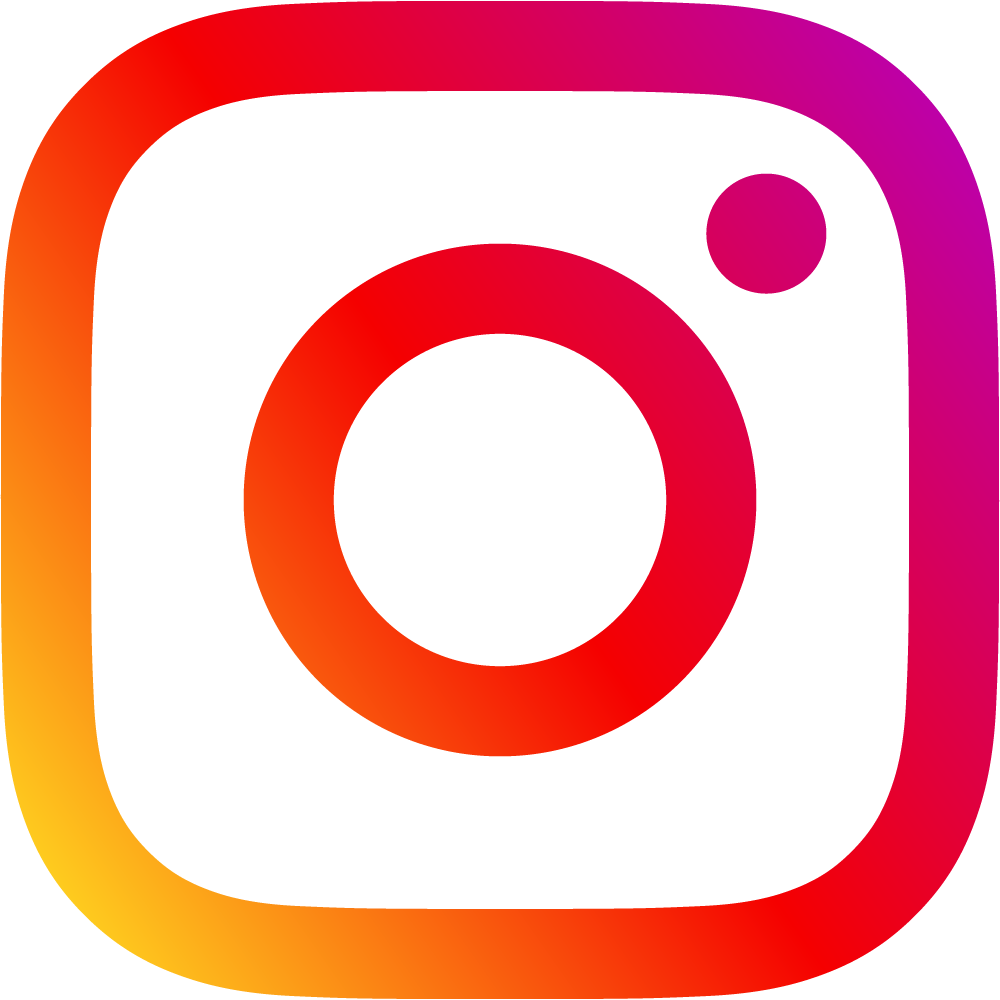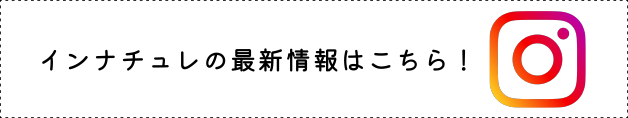第62回自分で育てたトマトは最高!

みなさん、こんにちは!
園芸研究家の矢澤秀成です。
気がつくと、このコラムも4年目に突入。
そこで、ちょっと手間がかかるけれど
収穫の感動が大きい!
「大玉トマト」に挑戦してみませんか。
1年目は5個ぐらいしかとれないかもしれないけど、
自分で作ったトマトは本当においしいですからね。
最初から「元を取ろう」とか欲を出さずに、
楽しみながら育てましょう。
ぜひ、みなさんにおいしいトマトを
つくっていただきたいので
今回は、トマトのコンパニオンプランツである
「ニラ」といっしょに植える方法をお伝えします!
最後まで、じっくり読んでみてくださいね。
目次
1:ニラといっしょにトマトの苗を植えよう!
4月になるとホームセンターの店頭に
トマトの苗が並び始めます。



でも、トマトの生育適温は20〜30℃なので
日中の気温が25℃ぐらい、
夜間の気温が15℃以上になってから
苗を植えるようにしましょう。
定植に適した場所は、風通しが良い日なた。
畑の場合は、定植の1か月ぐらい前から準備を始めます。
苦土石灰や牛ふん堆肥、緩効性化成肥料を
混合して土づくりをしてから畝を立てましょう。
畝の高さは15 cmぐらい。



そして、買ってきたトマトの苗は
定植の前日、深さ5cmぐらい水をためたバケツなどに
漬けて吸水させてから植えつけます。
苗を植える際の
トマトとトマトの株間は最低50 cm。
その間にニラ苗を2株ぐらい植えましょう。
トマトといっしょにニラを植える理由は、
ニラのニオイ成分に含まれる「アリシン」という物質が
カビ菌の繁殖を抑えてくれるから。
害虫もニラのニオイが嫌いです。
ただ植えておくだけでもいいんですけど、
ある程度伸びたらニラを細かくカットして
根元にバラバラとまいてあげると
効果が上がりますよ。
さらに効果を上げるには、
切ったニラの葉っぱをたたいて
ニオイ成分を出させる!
ぜひ、お試しください。

鉢やプランターに植える場合は、
トマト専用の培養土を活用したらいいと思います。
鉢は深い方がいいですね。
底面潅水式がベターです。
プランターも、深くて周りに支柱がさせるものがいいですね。
鉢やプランターに植えたら
雨の当たらない軒下に置くといいですよ。
2:水やりについて
植えつけ時の水やりはたっぷりと。
あとは、土の表面が乾いてきたら、しっかり与えます。
畑の場合、最初の植えつけ時だけで、
その後は、雨にまかせます。
1か月も雨が降らないような
よっぽど乾燥した天候でなければ
水やりはしないですね。
多くの方が、水をあげ過ぎて失敗しちゃうんです。
収穫期が梅雨にあたるので
雨にいっぱいあたって水分が多くなっちゃって
実が割れてしまう。
トマトは水抜き気味にした方が甘くなるし、
ちょっと皮が硬くなるんですけど、
湯むきをして食べると甘くておいしいですからね。
畑の場合は、マルチで調整しますよね。
マルチをかけていると水の吸収が減るので
植えつけ時に黒マルチを張ります。
マルチをかけた方が、
水はね・泥はねも防げていいですよ。

鉢やプランターの場合でも
水抜き気味の方がいいでしょう。
ただし、こちらは適度な水やりは必要。
葉っぱの様子を見ながら
しょげてくる前に水をあげてくださいね。
3:寒い日には低温対策を
苗が小さいうちは、
4月〜5月の突然やってくる寒さに注意しましょう。
夜間の気温が15℃を下回るような日には
苗にビニールをかけるなどの
「低温対策」が必要です。
面倒ですが、あったかい日中は外して
寒い夜間だけかぶせられるので
市販の苗キャップのような資材を使うとラクですよ。

あったかい瀬戸内沿岸部でも
過去に冷えたことはあるので
油断は禁物です。
4:支柱を立てよう!
大玉トマトの場合、茎を1本だけ伸ばして、
ある程度の高さになったら
頂上を摘心して、
花芽以外の、横から出てくる芽を取り除いて
大きな実をつけるように導きます。
なので、大玉トマトの実を支えるために
支柱は必ず立てましょう。
私は畑の場合、周囲にぐるっと支柱を立ててひもでくくり、
大きな行灯(あんどん)みたいにしちゃいますけど。


支柱の高さは1 m80cmを使っています。
30cmぐらいは地中に差し込むので
結局1 m50cmぐらいの高さになるかな。
丸い鉢の場合は、市販の行灯仕立ての支柱を
使ってもいいと思います。
支柱を立てるのは、植えつけの時。
その方が、あとから立てるより
根を傷めないんですよね。
支柱を立てたら
長めのビニールタイ(18 cm)、または麻紐などで
茎を支柱にゆるく結びつけます(誘引)。


風で揺れ動くので
ゆるく止めないと、
揺れるたびに傷んできちゃうんですよ。
だからビニタイは、ゆるく巻きつけておいた方が、
その後の生育がよくなりますよ。
5:肥料について
苗を植えつけたら2週間後に、
粒状の緩効性化成肥料を適量施します。

次の肥料は、1番下の実(最初の実)が収穫できる頃。
定植から1か月半ぐらい経っていると思うので
最初の収穫時に2回目の追肥をあげましょう。
肥料は、あんまりあげ過ぎると
病気が出やすくなっちゃうから、
養分は与え過ぎない方がいいです。
ニラについては、
肥料をあげてもあげなくても
ほったらかしで大丈夫ですよ!
6:成功のポイントは芽かき
トマトづくりに成功するかどうかは
「芽かき」次第。
茎のつけ根から出る脇芽をすべてつみ取るという
「芽かき作業」をしっかりやって
実を大きく育てましょう。
脇芽は、手で取り除きます。
芽が短いと取りにくいので
5 cmぐらい伸びたところを
パキッと折ります。
手で簡単に折れるので
ハサミは使わないでね。
また、この作業は「晴れた日」にやること。
昔から「脇芽つみは晴れた日にやれ」と
言われているのですが、これは
切り口に雨が侵入すると雑菌が入って、
そこから黒く腐ってしまうから。
気をつけてください。
脇芽をつまないと
ジャングルみたいに生い茂って日当たりも悪くなるし
枝葉が混み合うと梅雨明けのタイミングで
ダニが発生して葉っぱが枯れてしまいます。
しっかり脇芽をつむようにしてくださいね。
7:花が咲いたら雨よけの準備!
トマトの実は雨に当たると割れちゃうので、
雨に当てないようにしないといけません。
なので、最初の花が咲き終わったら
雨対策をしましょう。
苗が1〜2本ならば
支柱に透明ビニール傘をくくりつけて
雨よけにする。これでも十分ですよ。
ホームセンターに行くと
ビニールハウスのようなトマト用のビニール屋根や
適当なサイズにカットされたビニールも販売されています。
トマト用の支柱とセットになったものもありますよ。


気をつけたいのは「風通し」。
雨を防ぐビニールをかけるのは、
上の部分だけでサイドは開けること。
蒸れちゃうとよくないからね。
苗を植えつけるときに
屋根をつける方もいらっしゃるけれど
ダニが発生しやすくなるので
できれば花が咲き終わってから
ビニールをかけるようにしましょう。
8:先端を摘心しよう!
茎の先端が支柱の頂上近くまで伸びたら
(1m20cm〜30cmあたりが目安)
先端をカットします。
私は手でポキッと折るんですけどね。
茎が硬くて、ハサミを使う必要があるなら、
逆性石鹸で殺菌したハサミを使ってくださいね。
ハサミが媒介してウイルス病が広まることがあるので
できるだけハサミを使わない方がいいでしょう。
アルコールでも、ある程度、殺菌できるんだけど、
ウイルスを完全に殺すには不十分です。
菌類には効果があるんですけどね。
9:土寄せ
大きく成長してくると、
株元がだんだん持ち上がってきて
白い根が見えてくるようになります。
そうなる前に土寄せをしましょう。
雨が降ると畝の土が流れちゃうので
それを元に戻してあげるイメージですね。
10:収穫は手でもぎとろう!
収穫の際もハサミは使わず
手でもぎ取ったほうがいいですね。
茎のところを持ってボキッと折ります。
ちょっと傾ければ、ぽろっととれますよ。
11:注意したい病気と害虫!
気をつけたい病気は
モザイク病、黄化えそ病などのウイルス系の病気。
そして、うどん粉病、軟腐病など細菌系の病気ですね。
ウイルス系の病気は、薬で防げないので
見つけたら株ごと抜くしかないです。
葉っぱが萎縮して、くしゃってなっていたり
モザイク模様が出ていたり、
実の部分に筋が入っていたり
健全な実と比べて、見た目が明らかに不自然なので
見たらすぐわかると思います。
ウイルスにかかったら、もう駄目なのですぐ抜くこと!
決してハサミで切らないように!
ハサミを使い回すことでウイルスが
他に伝染しちゃいますから。
手でバキバキ折って、さっさと捨てましょう。
畑に残したままにすると
他の植物にうつっちゃう可能性もあるからね。
実は食べられるんですけど、私は食べないかな。
一方、気をつけたい害虫はアブラムシ、コナジラミ、
アザミウマ、ヨトウムシ、ガの幼虫など。
害虫については、殺虫剤を使うしかないんですが
「あんまり使いたくない」という人は
殺菌効果のある重曹スプレーを使ってみてください。
濃いのは駄目ですが、薄いもので回数を多く使うのは大丈夫ですよ。
通常の農薬は使用回数が決められているけれど
重曹なら回数を気にせず使えるというメリットもあります。
-225x300.jpg)

Q&A
Q:尻腐れ対策について教えてください。
A:トマトの「尻腐れ」は、実の先端部分が腐ったように黒くなること。実はカルシウム不足が原因で、株が病気になったわけではないです。私は、尻腐れが出たらカルシウムを与えるのですが、市販の尻腐れ予防スプレーなどを利用するといいと思います。その際、添付されている説明書をよく読んで用法を守って使ってくださいね。

第63回目は、カリブラコアについてお話しします。
4月23日ごろ投稿ですので、次回もお楽しみに!
投稿日:2025年4月9日